| フェローシップに正式に加入する前に、もう少しブリタニアの各地を回ってみることにした。 行ってない町もまだまだあるし、会うべき人物も多くいる。 まずは、フェローシップ幹部のエリザベスとエイブラハムの2人、そしてクラウンジュエル号を追うため、彼らが向かったと言われているジェロームが目標だ。 フェローシップへの加入は、色々な事が分かった後でも遅くはない。 |
 ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー スパーク
スパーク ウィリー
ウィリー スパーク
スパーク ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ウィリー
ウィリー ゲイ
ゲイ ゲイ
ゲイ ゲイ
ゲイ ゲイ
ゲイ ゲイ
ゲイ ゲイ
ゲイ コープ
コープ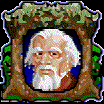 イオロ
イオロ コープ
コープ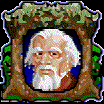 イオロ
イオロ コープ
コープ コープ
コープ コープ
コープ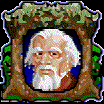 イオロ
イオロ コープ
コープ コープ
コープ コープ
コープ コープ
コープ レイモンド
レイモンド レイモンド
レイモンド レイモンド
レイモンド レイモンド
レイモンド レイモンド
レイモンド レイモンド
レイモンド ジェシー
ジェシー レイモンド
レイモンド| 以上でオーディションは終わり。 本物のアバタールだというのに、彼の劇のアバタール役の代役にすらなれませんでした。 演劇の道は厳しいものなのです。 |
| 続いては、トレーニング場へ行ってみた。 |
 セントリ
セントリ セントリ
セントリ セントリ
セントリ セントリ
セントリ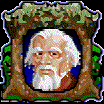 イオロ
イオロ セントリ
セントリ セントリ
セントリ シャミノ
シャミノ セントリ
セントリ
 セントリ
セントリ セントリ
セントリ セントリ
セントリ セントリ
セントリ| パーティーは8人まで組めるが、人によっては一定以上の人数だと加わってくれないようだ。 また、しばらく旅を続けてから彼を仲間に加えることにした。 ちなみにブリテインには、彼の他にも2人もトレーナーがいる。 競争過多にならないのだろうか…。 |
 ジュディス
ジュディス ジュディス
ジュディス ジュディス
ジュディス ネノ
ネノ ネノ
ネノ ジュディス
ジュディス ネノ
ネノ ネノ
ネノ ジュディス
ジュディス ジュディス
ジュディス ジュディス
ジュディス ジュディス
ジュディス ジュディス
ジュディス| そんなわけで、パターソン市長を調べてみることにした。 彼は、毎晩深夜0時に終わるフェローシップのミーティングに出席しているので、ホールの外で彼を市長を待ち伏せして尾行した。 すると、彼は真っ直ぐ自宅には帰らず、別の家に入って行く。 そこは、あの博物館長キャンディスの家であった。 ついに現場を目撃した! |
 キャンディス
キャンディス パターソン
パターソン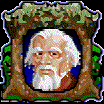 イオロ
イオロ パターソン
パターソン| と、色々な人と話したが、キリがないので、そろそろ次の目的地ジェロームへと向かう。 これだけ話しても、ブリテインにはまだまだ多くの住民が暮らしているので、機会があったら少しずつ紹介していきたい。 |
| ジェロームは大陸の南西の島にある都市なので、通常は船を使わないと行くことができない。 現状でも船は用意できないことはないが、海路を使ったとしても、大陸をグルッと大回りしなくてはならないため、非常に時間がかかってしまう。 しかし、ここで丁度良い方法が見つかった。 あのムーンゲートを使うのだ。 |
| ロード・ブリティッシュによると、魔法がおかしくなって以来、このムーンゲートは正しく機能しなくなっているそうだ。 見ると、一定の周期で光が歪んで波打ち、明らかに異常な様相である。 しかし、何度か試してみて分かったのだが、上手くタイミングを見て歪みの無い時に飛び込めば、従来通りワープができるのだ。 だが光が歪んでいる時に飛び込むと、弾かれてダメージを負う。 このタイミングは、なかなかシビアなので、HPが低い時には飛び込まない方が良いだろう。 |
| そして、以前は行き着く先は月の相によって変化したものだが、現在では決まった場所にワープするようになったようだ。 ブリテインのムーンゲートを潜った先は、六分儀で経緯度を計測するに、ジェロームの島である。 |
| ムーンゲートから少し歩くと、程なくジェロームの町に着いた。 危険があるとはいえ、一瞬にして目的地に着くことのできるムーンゲートは、やはり非常に便利だ。 次は、この町を探索する。 |