| まずは殺人事件の手がかりであるクラウン・ジュエル号を追ってブリテインへ行くことにした。 ロード・ブリティッシュにも会っておいた方が良いだろう。 トリンシックから北に伸びる道は、おそらくブリテインまで続いていると思われる。 昔と比べて道路もかなり整備されているから、迷うこともなさそうだ。 |
 ポール
ポール ポール
ポール ポール
ポール ポール
ポール ポール
ポール スパーク
スパーク ポール
ポール ダスティン
ダスティン メリル
メリル ダスティン
ダスティン メリル
メリル ダスティン
ダスティン ポール
ポール ポール
ポール ダスティン
ダスティン メリル
メリル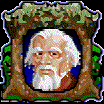 イオロ
イオロ ダスティン
ダスティン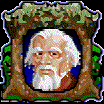 イオロ
イオロ


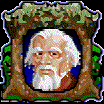 イオロ
イオロ| しかし、劇中に出てきた「仲間」、「支援者」、「主」というセリフ… これは、オープニングで赤い顔が言っていたものと同じ言葉だ。 スパークも赤い顔の夢を見たと言っていたが、フェローシップと何か関係があるのだろうか? |
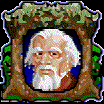 イオロ
イオロ スパーク
スパーク ポリー
ポリー ポリー
ポリー ポリー
ポリー ポリー
ポリー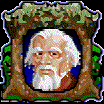

 ポリー
ポリー ポリー
ポリー ポリー
ポリー モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン モーフィン
モーフィン| 盗まれたシルバーサーペントの毒液とは、まるで麻薬や覚醒剤といったような薬であった。 小さな村の泥棒事件と思っていたが、思いのほか危険な事態である。 とりあえず、事件の全貌を知るべく、村中の人に話を聞いてみることにした。 |
 フェン
フェン コモル
コモル コモル
コモル フェン
フェン フェン
フェン コモル
コモル コモル
コモル フェン
フェン コモル
コモル フェン
フェン フェン
フェン コモル
コモル フェン
フェン コモル
コモル コモル
コモル フェン
フェン コモル
コモル フェン
フェン フェン
フェン フェン
フェン コモル
コモル コモル
コモル| ここにはフェローシップの救貧院があるようだが、あまり評判が良くないようだ。 後で、そちらの様子も見に行かないとならなそうだが、とりあえずは、この乞食の言っていたカミルという女性に会いに行くことにした。 |
 トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス トビアス
トビアス カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル カミル
カミル サーストン
サーストン サーストン
サーストン サーストン
サーストン サーストン
サーストン サーストン
サーストン サーストン
サーストン サーストン
サーストン| どうやら、この村の一部の人々の間では、フェローシップはあまり支持されていないようであった。 盗まれた毒液についての目ぼしい情報は手に入らないが、次はフェローシップのシェルターとやらに行ってみることにした。 |